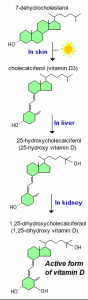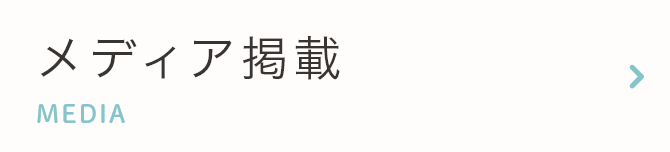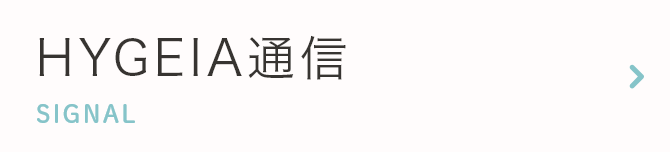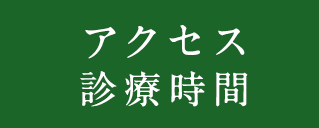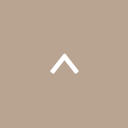変わった医者(4)
増永氏はこの本で、もうひとつの重要な東洋医学の特質についても述べている。 東洋医学の治療の根本は、経絡の異常を診断して調整をすることであるが、その基本は患者の体に触れることである。手を当て、異常を察知し、そして手を当てている行為そのものが即治療となる。その際の診断は、西洋医学の触診とはまったく意を異にするもので、これを切診と呼んでいる。
「近時この切診を応々西洋医学の触診と混同して理解されているようだが、触とは自他対立の感覚であるのに反し、切は接であり自他共感の支えによって成り立つことが忘れられている。切脈の場合に指先にふれているのは、その脈管の状態ではなくて、そこから全身の状態を共感する感覚である。触覚が高等な判別性感覚によっているのに対し、切診に働いているのは原始感覚による生命共感なのである。」
氏は、東洋医学と西洋医学の本質的な違いは、治療者と患者の間に起こる生命を持つもの同士の「共感」にあるという。言い換えれば心の交流といってもいいだろう。詳しくは省略するが、西洋医学的な触診に必要とされるものは触覚という判別性感覚であり、東洋医学の切診に必要とされるのは原始感覚であると氏は説明する。治療の対象として病変を見る西洋医学の立場とは違い、東洋医学の特質は原始感覚を用いて患者の体全体の「生命状態を共感」し、その立場を持って治療することにあるという。
「生体の歪みに対して、経穴は内蔵へ向かって液性伝導を行うのであるが、これを人為的に代行したとき、経絡のヒビキがおこると考えるのが妥当であろう。代行の仕方は人為的といっても自然に近い生命的なものでないといけない。経絡を上手に捉えられたのはこの東洋の自然生命観からの必然の帰結であったのだろう。私はこのような東洋の心がツボをとらえるためには一番大切だと考えている。ツボをとるときには探ってはいけない。盲人が手さぐりするのは触覚を鋭敏にし、物を判別しようとするからだが、その疑いの心から科学は発達し得ても、生命を摑むことはできない。生命には生命でもって対しなければならないのであって、ツボを知るのは原始感覚によって感じとるのである。患者の身になってというが、病苦に悩む心を知るのは生命共感のスキンシップである。スキンタッチは皮膚接触と訳されるが、生命共感のタッチとは深く挿入される接合である。皮膚にくい入る安定圧であり、しっかり抱き合う皮膚密着でないといけない。これを端的に示すのが握手である。握手は手の感触を判別するのではなく、手を通して心を感じ合うのである。このような皮膚結合によって生命共感は得られ、その原始感覚を通してツボは実感される。指はツボをおさえるのではなく、ツボに受取られて自づとツボにはまるのである。」
東洋医学的な思想のもとでは、人を治すのはあくまでも人である。皮膚を介した人間同士の心の交流があってこそ、患者の治る力が働くのである。それは決して一方通行ではなく、相互の作用がある。今風の言葉に直せば、インタラクティブな医療、とでも言おうか。不思議なことに実際、治療がうまくいったときは、治療をしている自分までも気持ちが良くなってしまう。これはこのような治療が一方的なものではなく、患者と医療者のコミュニケーション(言葉だけではない)である証拠のひとつだろう。現代医療では忘れられがちな、医療の根源的な部分が、そこにはある。
21世紀は心の時代であるとか、東洋の時代であるといわれるが、このような東洋医学の考え方は非常に21世紀的である、と思うのは私だけだろうか。
まだまだつづく。